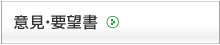有効期間について
問1:「重度の要介護状態」とは、要介護4または要介護5と理解してよろしいですか。
答:一般的には、重度の要介護者は今後も要介護度が変化しない見込みが比較的高く、要介護度が軽度の者は要介護認定後に適切なサービスを受けることにより要介護状態の改善が期待できることから、介護認定審査会において有効期間を原則の12ヶ月より長く定めることが可能な対象として、重度の要介護状態を基本と考えたものです。
なお、重度の要介護状態であれば、有効期間を一律に原則(12ヶ月)より長くするといった運用をするのではなく、介護認定審査会が、「現在の心身の状況がどの程度継続するか」という観点で、専門的見地から個々の事例に応じて判断すべきと考えます。
問2:有効期限を原則より長く定める場合の基準を示す予定はないのですか。
答:有効期間については、審査判定対象者の「現在の心身の状況がどの程度継続するか」との観点から検討を行うものであり、介護認定審査会が重度の要介護状態にある場合を基本として、専門的見地から個々の事例に応じて判断するものです。具体的な判断基準を示すことは考えておりません。
問3:要介護状態が軽度の方でも有効期間を24ヶ月とすることができると考えてよろしいですか。
答:すべての要介護度について、無原則に有効期間を原則より長く定めるのは好ましくなく、介護認定審査会において専門的見地から個々の事例に応じて有効期間を判断すべきと考えます。
問4:要介護認定の更新の結果、要介護度が変化した場合であっても、介護認定審査会が、審査判定対象者の身体上又は精神上の障害の程度が安定していると判断した場合、有効期間を24ヶ月とすることはできますか。
答:有効期間については、審査判定対象者の「現在の心身の状況がどの程度継続するか」との観点から検討を行うものであり、介護認定審査会が、専門的見地から個々の事例に応じて判断するものです。
無原則に有効期間を一律24ケ月に定めることは好ましくなく、介護認定審査会において専門的見地から個々の事例に応じて有効期間を判断すべきと考えます。
問5:要支援更新認定の結果、要介護となった場合及び要介護更新認定の結果、要支援となった場合の有効期間を教えてください。
答:有効期間は、原則6カ月となります。
問6:要支援の方においても、身体上又は精神上の障害の程度が安定している場合が多くありますが、有効期間を延長してよろしいでしょうか。
答:要支援状態の状態にある者とは「要介護状態となるおそれがある状態にある者」であり、身体上又は精神上の障害の程度が安定していないため、有効期間の拡大はできません。
問7:有効期間の拡大について、平成16年4月1日以降の審査判定者から適用することはできませんか。
答:平成16年4月1日以降に受理した要介護(要支援)更新認定申請から適用されます。介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2条の規定により、平成16年4月1日以前に受理した要介護(要支援)更新認定申請については、従前の例によることとされており、改正後の規定を適用することはできません。
介護認定審査会の定数について
問8:介護認定審査会(合議体)の委員定数を5人より少なく設置できる条件(「要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合」、「委員の確保が著しく困難な場合」)はすべて満たされなければならないのでしょうか。
答:すべてを満たさなければならないというものではありませんが、5人より少ない定数によっても介護認定審査会の審査判定の質が維持されるものと市町村が判断した場合、5人より少ない人数を定めることができます。
いずれにしても、介護認定審査会委員(合議体の委員)、関係団体等と十分に協議を行った上で判断してください。
〈参考 介護認定審査会運営要綱 2 認定審査会の委員の構成 2)合議体の設置 より〉
合議体の委員の定数については、以下の場合などにおいて、5人より少ない定数によっても認定審査会の審査判定の質が維持されるものと市町村が判断した場合、5人より少ない人数を定めることができる。ただし、この場合であっても、少なくとも3人を下回って定めることはできない。
・要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合
・委員の確保が著しく困難な場合
問9:委員定数が5人より少ない人数であっても運営が可能であると市町村が判断する基準を示してください。
答:委員定数が5人より少ない人数であっても、介護認定審査会の審査判定の質が維持され、これまでと同様に円滑に審査判定が行われる場合であると考えます。
具体的には、
・要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合
・委員の確保が著しく困難な場合
を想定しております。
いずれにしても、介護認定審査会委員(合議体の委員)、関係団体等と十分協議を行った上で判断してください。
問10:介護認定審査会(合議体)の定数を3人とした場合、委員は、保健、医療、福祉の各分野からの構成にしなければならないのですか。
答:介護認定審査会(合議体)は、保健・医療・福祉の各分野の均衡に配慮した構成とする必要があります。
この場合、介護認定審査会会長(合議体の長)は、いずれかの専門分野の学識経験者となりますが、専門性を発揮しつつ、介護認定審査会の長(合議体の長)としての普遍性をも併せもって、介護認定審査会(合議体)の運営に当たる必要があります。
なお、従来からも、保健、医療、福祉のいずれかの委員が欠席した場合には、介護認定審査会(合議体)を開催しないことが望ましいとしております。
問11:合議体の委員定数を3人とした場合、2人の委員の出席で合議体を開催することはできますか。
答:お問い合わせのような事態が生じないように、日程調整等の工夫を行ってください。
なお、従来からも「特定の分野の委員の確保が困難な場合にあっては、当該分野の委員を他の分野より多く合議体に所属させることとした上で、会議の開催にあたって、定足数を満たすような必要な人数が交替に出席する方式でも差し支えない。」としております。このように、3名の出席を実現するために運営上の工夫を行うことは差し支えありません。
問12:合議体の委員定数を3人とした場合、会議の開催にあたり、定足数を満たさない場合、無任所の委員の出席により開催してもよろしいですか。
答:差し支えありません。
ただし、そのような場合は、当該委員が、当該審査判定対象者に対して認定調査を行っていないこと、当該委員が当該審査判定対象者の入院(入所)している(あるいは介護サービスを受けている)施設に所属していないことなどについて十分留意する必要があります。
問13:合議体の出席者が過半数に満たない場合、同日に開催している別の合議体の委員の出席により開催してもよろしいですか。
答:合議体の出席者が過半数に満たない場合、やむを得ない場合として、同日に開催している別の合議体の委員の出席により開催することも可能です。
ただし、そのような場合は、当該委員が、当該審査判定対象者に対して認定調査を行っていないこと、当該委員が当該審査判定対象者の入院(入所)している(あるいは介護サービスを受けている)施設に所属していないことなどについて十分留意する必要があります。
問14:委員定数を3人とした場合、3人の出席により会議を開催することになりますが、会議の議事において可否同数の場合は、介護認定審査会会長(合議体の長)の意見により決定することでよろしいでしょうか。
答:会議の議事は、出席した委員の過半数により決定します。可否が同数の場合は、介護認定審査会会長(合議体の長)の意見により決定することになります。
ただし、委員間の意見調整を行うことにより、可能な限り当該審査判定における合意を得られるようにすることに留意してください。
問15:市町村が介護認定審査会の質を確保できると判断した場合、新規申請あるいは区分変更申請についても、3人で審査判定を行うことは可能ですか。
答:市町村の実情及びそれに基づく市町村の判断により可能な場合もありますが、その場合であっても、審査判定がこれまでと同様に円滑に審査判定が行われ、審査判定の内容にも支障を来さない場合であると考えます。また、この場合であっても、3人を下回って定めることはできません。
いずれにしても、介護認定審査会の審査判定の質が確保されるよう、介護認定審査会委員(合議体の委員)、関係団体等と十分に協議を行った上で判断してください。
平成16年4月16日現在